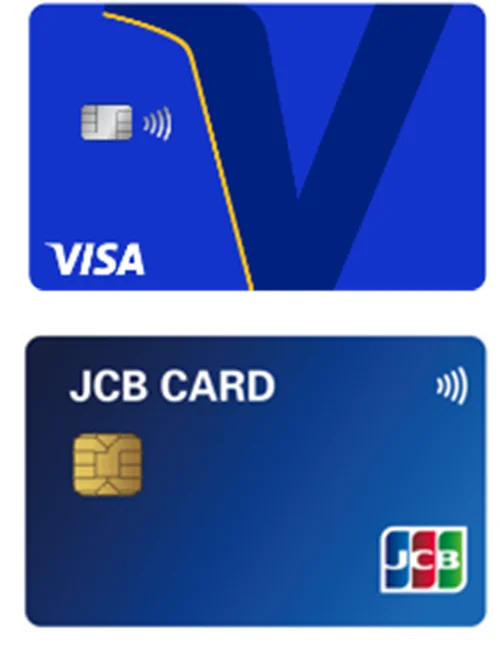都営地下鉄のタッチ決済、9/10始発で55駅に拡大
ベストカレンダー編集部
2025年9月8日 14:22
都営地下鉄タッチ決済拡大
開催日:9月10日

都営地下鉄で広がる「カード・スマホのタッチ」で乗車する新たな選択肢
東京都交通局と三井住友カード、株式会社ジェーシービー(JCB)、日本信号、オムロン ソーシアルソリューションズ、QUADRACが連携し、クレジットカード等のタッチ決済を用いた乗車サービスの実証実験が拡大されます。発表は2025年9月8日14時に行われ、令和6年12月に浅草線・大江戸線の26駅で開始した実験を、令和7年9月10日(水)始発から55駅へと拡大します。
この拡大により、都営地下鉄全106駅のうち55駅で、タッチ決済による乗車サービスが利用可能になります。拡大は段階的に進められ、令和7年度内に全駅への導入を予定していることも明記されています。対象となるのは、タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、これらのカードを設定したスマートフォン等です。
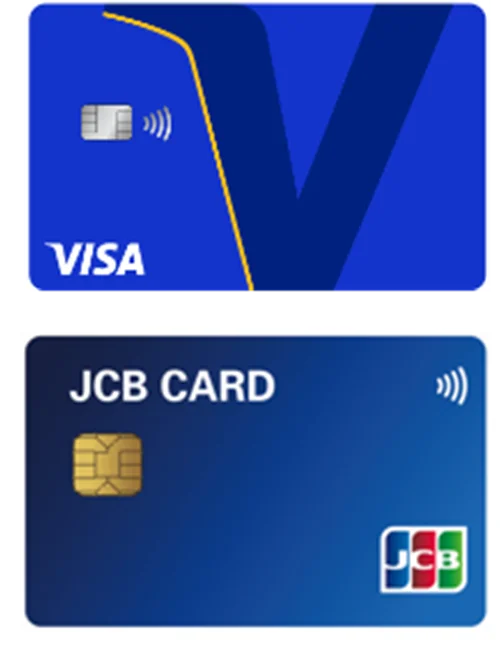
利用方法と適用開始の時刻、対象駅の詳細
乗車方法はシンプルです。手元のタッチ決済対応カードやスマートフォンを、乗降車時に設置された専用リーダにタッチするだけで改札の入出場が可能になります。暗証番号やサインが不要で、短時間での通過を想定しています(一定金額以上の支払い時は別途本人確認が必要となります)。
利用開始は令和7年9月10日(水)の始発からです。拡大対象となる駅は浅草線・大江戸線・三田線の合計55駅で、以下に各線ごとの駅を列記します。駅名はプレスリリースに沿って表記しています。

乗車方法と開始時期の補足説明
乗車方法:タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、それらが設定されたスマートフォン等を、乗降車時に専用リーダにタッチします。サインや暗証番号の入力は基本的に不要で、スピーディーに乗降が可能です。
開始時期:令和7年9月10日(水)始発より利用可能となります。初期実験は令和6年12月に浅草線・大江戸線26駅で開始されており、今回の拡大はその適用範囲を拡充するものです。
利用可能駅一覧(詳述)
以下に、各路線ごとの利用可能駅を示します。都営浅草線は12駅から17駅へ、都営大江戸線は13駅から37駅へ拡大し、都営三田線は1駅のままです。合計で55駅が利用対象となります。
駅名はプレスリリースの表記順に掲載しています。
- 都営浅草線(12駅⇒17駅)
- 西馬込駅
- 馬込駅
- 中延駅
- 戸越駅
- 五反田駅
- 高輪台駅
- 泉岳寺駅
- 三田駅
- 大門駅
- 新橋駅
- 東銀座駅
- 宝町駅
- 日本橋駅
- 人形町駅
- 浅草橋駅
- 浅草駅
- 本所吾妻橋駅
- 都営大江戸線(13駅⇒37駅)
- 新宿西口駅
- 東新宿駅
- 若松河田駅
- 牛込柳町駅
- 牛込神楽坂駅
- 飯田橋駅
- 春日駅
- 本郷三丁目駅
- 上野御徒町駅
- 新御徒町駅
- 両国駅
- 森下駅
- 清澄白河駅
- 門前仲町駅
- 月島駅
- 勝どき駅
- 築地市場駅
- 汐留駅
- 大門駅
- 赤羽橋駅
- 麻布十番駅
- 六本木駅
- 青山一丁目駅
- 国立競技場駅
- 代々木駅
- 新宿駅
- 都庁前駅
- 西新宿五丁目駅
- 中野坂上駅
- 東中野駅
- 中井駅
- 落合南長崎駅
- 新江古田駅
- 練馬駅
- 豊島園駅
- 練馬春日町駅
- 光が丘駅
- 都営三田線(現状:1駅)
- 三田駅
決済ブランド、各社の役割と利用履歴の確認方法
本実証実験で利用可能な決済ブランドは以下のとおりです。国際的に普及している主要ブランドが揃っており、幅広いカード・決済媒体に対応します。
対応ブランド:Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯(UnionPay)。
各社の具体的な役割
実験には複数の事業者が参加しており、それぞれの専門性に基づいて役割分担が行われています。以下の表で整理します。
| 企業名 | 主な役割 |
|---|---|
| 東京都交通局 | 鉄道の運行、タッチ決済対応設備の整備、タッチ決済を使用した企画の実施 |
| 三井住友カード株式会社 | stera transitプラットフォーム提供、キャッシュレス決済導入支援、Visa・Mastercard・銀聯の導入支援および認知プロモーション |
| 株式会社ジェーシービー(JCB) | キャッシュレス決済導入支援、JCBおよびAmerican Express、Diners Club、Discoverのタッチ決済に関するソリューション提供・認知プロモーション |
| 日本信号株式会社 | タッチ決済対応改札機の開発 |
| オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | タッチ決済対応改札機の開発 |
| QUADRAC株式会社 | 交通事業者向け決済および認証に関するSaaS型プラットフォーム「Q-move」の提供、タッチ決済履歴の確認手段の提供 |
タッチ決済履歴の確認方法
タッチ決済の利用履歴は、QUADRACが提供する「Q-move」サイトで確認できます。サイトにアクセスして「マイページ」の会員登録を完了すると、履歴の参照が可能になります。Q-moveのURLはプレスリリースで案内されています。
参考URL:https://q-move.info/
タッチ決済の技術的特徴とstera transitの役割
タッチ決済は、国内外で採用されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用する決済方式です。利用者は対応端末にカードやスマホをタッチするだけで決済が完了し、サインや暗証番号が不要になる場面が多く、迅速な処理が可能です。
ただし、プレスリリースでは一定金額以上の支払いについてはカード挿入と暗証番号入力、またはサインによる本人確認が必要になることが注記されています。公共交通機関における導入は、日常の利用シーンの利便性向上だけでなく、インバウンド対応や地域のキャッシュレス化推進にも寄与することが期待されています。
stera transitについての説明
「stera transit」は三井住友カードが提供する公共交通機関向けのタッチ決済ソリューションです。三井住友カードがGMOペイメントゲートウェイ、GMOフィナンシャルゲートおよびVisaと共同で構築した事業者向け決済プラットフォーム「stera」を基盤に、国際ブランドの非接触決済(タッチ決済)を活用します。
stera transitは、現金や事前チャージの不要化による利用者利便性の向上に加え、MaaSやスマートシティの認証基盤としての活用が可能であり、今後全国での導入が予定されていると説明されています。詳細は三井住友カードのstera transitのページで案内されています。
拡大内容の要点整理(表)と締めくくりの説明
以下の表は、本記事で示した主な事項を整理したものです。項目ごとに実施主体、対象、開始時期、対応ブランド、利用確認手段などをまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2025年9月8日 14時(JCBによるプレスリリース) |
| 拡大適用開始 | 令和7年9月10日(水)始発より |
| 実施主体(参加企業) | 東京都交通局、三井住友カード、株式会社ジェーシービー、日本信号、オムロン ソーシアルソリューションズ、QUADRAC |
| 対象路線・駅数 | 都営浅草線・大江戸線・三田線の合計55駅(都営地下鉄全106駅中55駅で利用可能) |
| 利用可能媒体 | タッチ決済対応カード(クレジット・デビット・プリペイド)および同カードが設定されたスマートフォン等 |
| 対応ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯 |
| 利用履歴の確認 | QUADRACの「Q-move」サイト(https://q-move.info/)のマイページ登録により確認可 |
| 技術基盤 | 三井住友カードの「stera transit」プラットフォームおよび国際ブランドの非接触決済技術 |
| 備考 | 令和6年12月に26駅で実証実験を開始。令和7年度内に都営地下鉄全駅への拡大を予定。一定金額以上の支払いは本人確認が必要 |
今回の拡大により、タッチ決済を利用した乗車サービスがより多くの駅で利用可能になります。利用に際しては、対応カードや端末の確認、決済履歴の確認方法(Q-moveの登録)など事前の準備が必要です。各社の役割分担や技術的な仕組みについては上記のとおり整理しました。