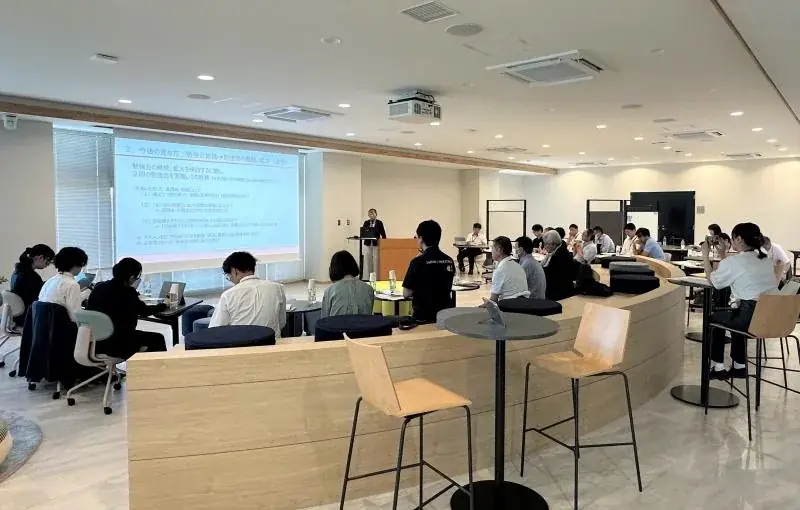岡山大学主催 岡山県の人口減少対策を議論した勉強会
ベストカレンダー編集部
2025年9月28日 16:59
岡山県の人口減少勉強会
開催期間:7月22日〜8月21日

地域の課題を共有する場として開かれた勉強会の意義
国立大学法人岡山大学が事務局を務めるおかやま地域発展協議体は、「岡山県の人口減少問題に関する今後の取り組み方について」をテーマとした勉強会を2025年7月22日と8月21日の2回にわたり開催しました。本勉強会は、岡山県全体が抱える重要課題である人口減少に対して、地域内の各団体が現状を共有し、協働できる方策を模索することを目的としています。
プレスリリースは2025年9月28日に公表され、主催は国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)です。勉強会は同大学の津島キャンパスで実施され、創立五十周年記念館(7月22日)および共創イノベーションラボ(KIBINOVE:きびのべ)(8月21日)が会場となりました。

開催背景と目的
岡山県では人口減少が深刻な地域課題となっており、多様な主体が連携して取り組む必要があります。本勉強会は、まず各団体が取り組んでいる施策やデータの共有を行い、その上でおかやま地域発展協議体としての活動方針や連携の在り方について意見交換を行うことを目指しました。
会場はいずれも岡山大学津島キャンパス内で、大学が地域との接点を持ちやすい場を提供することで、大学・自治体・企業・教育機関など多様な関係者が参加しやすい構成となっています。

共有された情報と議論の中核
情報共有のセッションでは、参加団体が人口動態を的確に把握し、それに基づいた対応を進めていることが確認されました。特にデータに基づく現状分析が重視され、地域ごとの傾向や若年層の流出状況などが整理されました。
意見交換では、教育・雇用・地域魅力の3点を巡る課題認識が中心に置かれました。具体的には、進学や就職の段階で地方から都市へ人材が流出する傾向、都市で就職した後に転職などを機に岡山県へ戻る動機づけが不足していることなどが指摘されました。

主な議論のポイント
- データと対策の整合性:参加団体は人口の動態を把握しデータに基づく施策を進めている点で共通認識を持ちました。
- 若年層流出の要因:進学・就職時に地方→都市へ流れてしまう構造、その後の転職時に岡山へ戻るための環境整備の必要性が議論されました。
- アプローチの多様性:各団体の取り組みはアプローチが異なるため、互いの手法や成果を比較・学習することの重要性が示されました。
議論は活発に行われ、参加者間で具体的な課題指摘や提案が交わされました。勉強会は単なる情報の提示にとどまらず、実践的な検討の場となったと整理できます。

開催後の見解と大学の役割
第2回の勉強会終了後、三村由香里理事(企画・評価・総務担当)は、各団体がそれぞれ異なるアプローチで人口減少問題に取り組んでいる点に触れ、「これからの取り組みを考える際にこの勉強会が良いきっかけになれば」と述べています。大学が事務局として場を整備したことにより、多様な主体のつながりを育む第一歩となったことが示唆されました。
岡山大学は引き続き、おかやま地域発展協議体を通じて地域連携を重視し、地域づくりへの協力を継続する旨を明らかにしています。こうした活動は大学の研究・教育機能を地域課題の解決に結びつける取り組みの一環でもあります。

大学の関連施策と外部評価
岡山大学は国連のSDGsを支援しており、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。また、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択され、地域との共創や大学の研究基盤強化を推進しています。
大学内の関連組織としては、岡山大学研究・イノベーション共創機構や共創イノベーションラボ(KIBINOVE)などがあり、産学共創やスタートアップ支援、研究機器の共用など多面的な連携基盤が整備されています。

参照情報、連絡先、関連リンク—詳細な実務情報
以下に、勉強会の詳細および参照可能な組織・連絡先を整理します。プレスリリースでは連絡先や関連機関のURL、問い合わせ窓口が具体的に示されています。
お問い合わせ先には岡山大学学都おかやま共創本部(研究・イノベーション共創管理統括部 社会共創課)をはじめとした複数の窓口が示されています。メールアドレスはプレスリリース原文の通り、記載時に「◎」で「@」を置き換えた表記になっていますので、その点を留意してください。
- 主催
- 国立大学法人岡山大学(おかやま地域発展協議体 事務局)
- 開催日
- 第1回:2025年7月22日(創立五十周年記念館)/第2回:2025年8月21日(共創イノベーションラボ KIBINOVE)
- プレスリリース公表日
- 2025年9月28日
- 大学所在地
- 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1(津島キャンパス 本部棟)
- おかやま地域発展協議体: http://okayama-association.jp/
- 岡山大学研究・イノベーション共創機構: https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
- KIBINOVE(共創イノベーションラボ): https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/
- プレスリリース(岡山大学): https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14573.html
- 各種メディアや関連情報(OTD、YouTube、J-PEAKS等)については本文末の一覧を参照ください。

主要な問い合わせ先(原文の表記に準拠)
以下はプレスリリースで示された各窓口情報です。メールアドレス表記では「◎」が「@」の代替文字として用いられています。
- 岡山大学 学都おかやま共創本部(研究・イノベーション共創管理統括部 社会共創課)
- 住所: 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟
- TEL: 086-251-8855
- E-mail: gakuto◎adm.okayama-u.ac.jp(◎を@に置き換え)
- 岡山大学病院 新医療研究開発センター(製薬・医療機器企業関係者向け)
- 住所: 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
- お問い合わせ: http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
- 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当(医療関係者・研究者向け)
- TEL: 086-235-7983
- E-mail: ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp(◎を@に置き換え)
- URL: http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
- 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
- TEL: 086-251-8463
- E-mail: sangaku◎okayama-u.ac.jp(◎を@に置き換え)
- URL: https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
- 研究機器共用関連(チーム共用)
- TEL: 086-251-8705 / FAX: 086-251-7114
- E-mail: cfp◎okayama-u.ac.jp(◎を@に置き換え)
- URL: https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
- スタートアップ・ベンチャー関連(スタートアップ・ベンチャー創出本部)
- E-mail: start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp(◎を@に置き換え)
- URL: https://venture.okayama-u.ac.jp/
勉強会の要点整理(表形式)
以下の表は、本稿で取り上げた勉強会の主要情報を項目ごとに整理したものです。会場・日時・主催・議論のポイントおよび参照リンクを一目で確認できるように構成しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主題 | 岡山県の人口減少問題に関する今後の取り組み方について |
| 主催 | 国立大学法人岡山大学(おかやま地域発展協議体 事務局) |
| 開催日と会場 | 2025年7月22日(創立五十周年記念館)/2025年8月21日(共創イノベーションラボ KIBINOVE) |
| 目的 | 各団体の取り組み共有およびおかやま地域発展協議体としての今後の連携の方向性に関する意見交換 |
| 主な議論のポイント | データに基づく人口動態把握/進学・就職時の若年層流出/都市で就職後の県内復帰の動機づけ/取り組みの多様性 |
| 大学側の発言 | 三村由香里理事(企画・評価・総務担当)の発言:「各団体が取り組まれている人口減少問題は、アプローチの違うところがあるので、これからの取り組みを考える際にこの勉強会が良いきっかけになれば」 |
| 参照リンク | プレスリリース: https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14573.html/おかやま地域発展協議体: http://okayama-association.jp//KIBINOVE: https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/ |
| 連絡先(代表) | 岡山大学 学都おかやま共創本部(社会共創課)TEL: 086-251-8855 E-mail: gakuto◎adm.okayama-u.ac.jp(◎を@に置き換え) |
本稿はプレスリリースの全文に基づき、開催の背景、議論の内容、関係機関と連絡先を整理した。地域の人口減少という公的課題に対して、大学がコーディネータ役を担いながら多様な主体が情報を持ち寄り、共通の認識形成と連携の方向を探る試みであることが確認できる。
参考リンク: